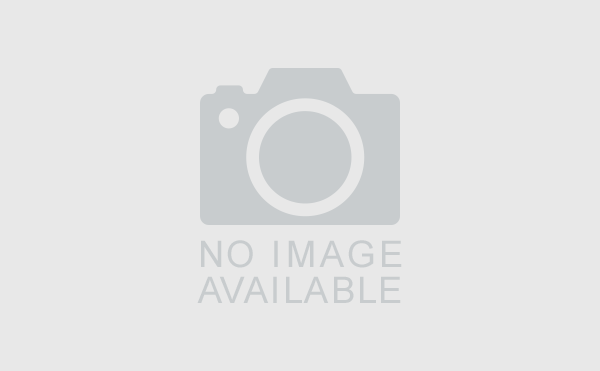みんな違ってみんな良い

滋賀県大津市瀬田のトレーニングジム 女性専用フィットネスLBCです。
知識や真理を探求する過程で「一つの理論には必ず一つ以上の反論が存在しそれらをすり合わせてより良い答えを求める」というアウフヘーベンという考えを私は大切にしています。
この視点は知の進化の本質を鋭く捉えています。
ヘーゲルの弁証法に由来するアウフヘーベンとは単なる妥協ではなく、正と反の対立を「止揚」し、両者を包含した新たな段階へと引き上げる創造的なプロセスで、どのような理論にも完全無欠なものは無く、必ず反論や異なる視点が存在すると言う考えの上に成り立ちます。
それらを正面から受け止め、統合する事で知識はより深く、洗練されたものへと進化します。
この考えは数学のような一見絶対的な分野にも当てはまり、たとえば「1+1=2」という命題は日常的には自明ですが、数学の基礎を掘り下げると、反論の可能性が見えてきます。
モジュロ2の計算では1+1=0となり、非標準モデルでは「1」や「2」の定義自体が揺らぎます。
哲学的には直観主義や形式主義の立場から「1+1=2」の意味を問い直すと、真理は特定の公理系に依存した相対的なものになります。
さらに現実世界では、1滴の水+1滴の水が1滴になったり、1匹のウサギ+1匹のウサギが繁殖して3匹になったりと、2以外の結果が生じることもあります。
これらの反論は数学が単なる計算の体系ではなく、創造的で動的な知の営みであることを示しています。
同様の多角的視点は筋力トレーニングの世界にも見られ、たとえばスクワットという一つの動作を取っても、その解釈やアプローチは目的によって異なります。
ボディーメイクを目指す方は筋肥大を重視し、重い重量で低回数のセットを組むかもしれませんし、一方で競技能力の向上を求めるアスリートは爆発的なパワーやスピードを優先し、高速で軽めの負荷を扱うかもしれません。
更に健康を求める一般の方なら、怪我を避けつつ全身のバランスを整える為に軽い重量で高回数の動作を選ぶかもしれません。
同じスクワットという「基本」を共有しながら、目的や視点によってやり方や解釈は異なるのです。
この多様性は「見る角度で解釈が変わる」ことの好例であり、基本と目的を理解すれば「みんな違ってみんな良い」という共存が可能になります。
しかしこうした多角的視点の重要性を理解しないまま、物事を安直に一面的な視点で断定する姿勢も見受けられます。
特にSNSや動画配信プラットフォームでは、「○○だから~~だ」と強い言葉で論破を試みるインフルエンサーが散見されます。
このような一方的で過激な主張は、議論を深めるどころか思考を閉ざしていると言わざるを得ません。
たとえば「このトレーニング法が絶対!」と断言する動画や、「この理論だけが正しい」と決めつけるコンテンツは、異なる視点や反論を無視し、対話の可能性を狭めてしまいます。
このような姿勢は知的な探求とは程遠く、表面的な注目を集めるための手法に過ぎません。
視聴者としては、こうした安直な論破スタイルに接すると、物足りなさや違和感を覚えるのではないでしょうか?
対照的に異なる視点を紹介し、「一緒に考えてみましょう」と呼びかける発信者は、知的好奇心を刺激し、深い学びを提供してくれます。
ここで鍵となるのが「発想の転換」です。
数学史を振り返れば負の数、虚数、非ユークリッド幾何学といった革新的な概念はすべて常識を疑う大胆な発想から生まれました。
ガロアの群論やリーマンの曲がった空間も、従来の枠組みを超えたひらめきがなければ存在しません。
筋力トレーニングでも「高負荷が筋肥大に最適」という常識を疑い、低負荷高回数でも筋成長が可能なことを示した研究は、発想の転換が新たな知見を生んだ好例です。
発想の転換は反論や異なる視点を否定として退けるのではなく、新たな理論や実践の種として育てる力を持ちます。
アウフヘーベンはこの発想の転換を通じて対立する視点を統合し、知や技術を次の段階へと押し上げます。
ただしすべての反論や視点が等しく価値があるわけでは無く、どの反論が本質的でどの視点が単なるノイズかを峻別する眼が求められます。
数学では公理系の選択が議論の方向を定め、トレーニングでは個々の目的や身体の状態が最適な方法を決めます。
議論や実践が散漫になれば、アウフヘーベンの目指す「より良い答え」は遠ざかってしまいます。
数学、トレーニング、情報発信とあらゆる分野において、発想の転換と多角的視点の統合が新たな地平を拓きます。
しかし、その過程は容易ではありません。
常識を疑い、異なる視点を積極的に取り入れる勇気と、それを整理し統合する知恵が必要です。
真理の探求とは、反論を恐れず多様な視点を認め、発想を転換させながら対立を乗り越える旅です。
アウフヘーベンは、その旅路で私たちを導く羅針盤です。
たとえ「1+1=2」のような自明な命題や、スクワットのような基本動作、SNSでの発信であっても視点や目的を変えれば新たな解釈が生まれます。
安直な断定を避け、基本と目的を理解し、多様性を認めれば数学もトレーニングも、情報発信もすべての知と実践は無限の可能性を秘めています。
私たちはこの対話と探求を通じて、どこまで真理に近づけるでしょうか。
その答えは、さらなる発想の転換と視点の統合の中にあります。
本質を理解し真理を求める探求心さえあれば「みんな違ってみんな良い」と言う話です。
滋賀県大津市月輪1丁目3-8 アル・プラザ瀬田4F 女性専用フィットネスLBC
無料体験随時受付中