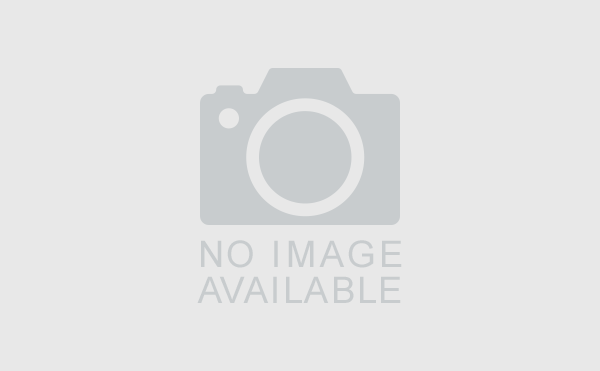行動変容は「小さなステップ」と「環境調整」

滋賀県大津市瀬田のトレーニングジム 女性専用フィットネスLBCです。
肥満の人に向けられるアドバイスとして最も多いのが「もっと食べる量を減らして、運動を増やしてください」というものです。
しかしこうしたアドバイスは多くの人にとって効果がないだけでなく有害な可能性もあると、イギリスのシェフィールド大学で栄養学上級講師を務めるルーシー・ニールド氏は主張されます。
確かにニールド氏らが指摘するように「肥満は単なる意志力の問題ではなく、複雑で慢性的な再発性の病気」であり、イングランドでは成人の約26.5%、子どもの約22.1%が肥満の影響を受けているとの報告もされています(NHSデータ)。
この主張は肥満が生物学的要因(遺伝やホルモン異常)、環境的要因(食品の入手しやすさ)、社会的要因(ストレスや経済状況)が絡む多面的な問題であることを示しており、科学的には妥当です。
たとえばThe Lancet(2021年)の研究では、超加工食品の消費が体重増加と強い相関を持つことが示されています。
しかしこのような学術的な説明は、日常の観察と向き合うとどこか違和感を覚えることも事実です。
フィッシュ&チップスやパブ文化が根強いイングランドにおいて、肥満問題の背景には個人の食習慣や「常識のズレ」が大きく関与していると感じられるからです。
多くの場合、肥満を抱える人々はコーラやお菓子といった高カロリー・低栄養食品を日常的に摂取する事にに抵抗が少ない傾向があります。
たとえば「ゼロカロリー飲料は美味しくない」と拒否し、代わりに「お茶を飲む」という提案にも耳を貸さないケースも多く見られます。
この行動は、Health Psychologyの研究が指摘するように、即時的な快楽を求める脳の報酬系(ドーパミン分泌)と深く関係しています。
フィッシュ&チップスのような文化的で身近な食事が日常に根付いている場合、ささみやブロッコリーのような低カロリーな選択肢に切り替えるのは単なる知識の問題を超え、習慣や感情の壁に阻まれることが多いのです。
もちろん甲状腺機能低下や双極性障害の薬の副作用など、肥満の原因が病気や薬に起因する場合もあります。
BMJ(2020年)の研究によれば遺伝的要因は肥満リスクの30~70%を占め、環境や生活習慣が残りを構成します。
しかし、こうした要因を考慮しても、日常の食選択における「自分への甘さ」や「常識のズレ」が肥満の大きな要因であることは否定できません。
たとえばイングランドの糖税導入により、ソフトドリンクの糖分消費が20%減少したというデータ(The Lancet、2022年)は環境を変えることで行動変容を促す効果を示していますが、個人の意識改革が伴わなければ持続的な変化は難しいでしょう。
このような状況で、我々は肥満問題にどう向き合うべきでしょうか?
行動変容の研究では「小さなステップ」と「環境調整」が有効とされています。
例えばいきなりおやつをやめるのでは無くゼロカロリー飲料や低糖質の代替品から始める、あるいは家庭にお菓子を置かない環境を作るといった方法です。
しかし根本的には本人が変化を望む意識が不可欠です。
イングランドの肥満率の高さはフィッシュ&チップスに象徴される食文化と切り離せませんし、個人レベルでの努力に加えて政策的な介入や教育の強化が求められます。
たとえばオートミールやブロッコリーを工夫して取り入れる生活を実践する人々の姿勢は、自己管理の模範と言えるでしょう。
肥満問題は「複雑な病気」であると同時に、日常の小さな選択の積み重ねでもあります。
社会全体で「常識」を再定義し、健康的な選択を自然なものにする努力が今後の鍵となるでしょう。
もちろん食生活の改善も必須ですが、日常での運動習慣の定着も当然重要です。
今まで通りを変えられないなら何時までも今まで通りだと言う話です。
滋賀県大津市月輪1丁目3-8 アル・プラザ瀬田4F 女性専用フィットネスLBC
無料体験随時受付中