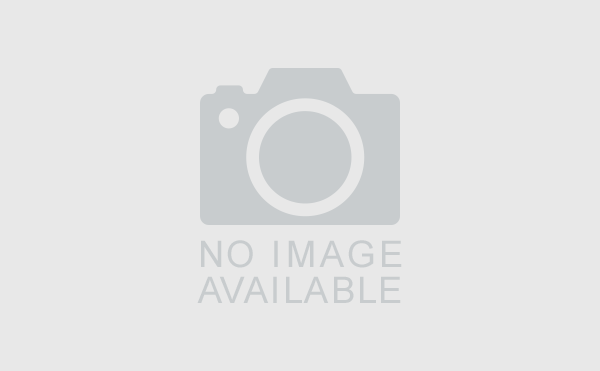見えない疲労を管理する

滋賀県大津市瀬田のトレーニングジム 女性専用フィットネスLBCです。
筋力トレーニングを行う際、特に高強度やコンパウンド種目を連日で行う事で「神経系の疲労」がパフォーマンスに影響を与えることがあります。
仮に月曜日に下半身、火曜日に胸のトレーニングを行った場合の神経系の疲労、特に「運動単位」と「活動電位の発火頻度」の影響について科学的エビデンスに基づいて説明した文は以下の通りです。
神経系の疲労とは?
筋力トレーニングは筋繊維だけでなく神経系にも大きな負荷をかけます。
神経系の疲労は主に中枢神経系(CNS)と末梢神経系に分けられ、高強度トレーニング(最大挙上重量の80%以上)やスクワットやデッドリフトのようなコンパウンド種目は全身の筋群を動員する為に特に中枢神経系に強いストレスを与えます。
研究によれば中枢神経系の回復には通常48〜72時間かかるとされており、筋繊維の回復(24〜48時間)よりも時間がかかることが一般的です(Kraemer & Ratamess, 2004)。
月曜の下半身トレーニングが火曜の胸トレーニングに与える影響
仮に月曜日に高強度・高ボリュームの下半身トレーニング(例:スクワットやデッドリフトを5セット×3〜5レップ、1RMの80%以上)を行った場合、火曜日の胸トレーニング(例:ベンチプレス)にどの程度の影響があるのでしょうか?
以下で、運動単位と活動電位の観点から見ていきます。
運動単位への影響
運動単位とは運動ニューロンとそれが支配する筋繊維のセットを指します。
筋力発揮には運動単位の発火頻度や同期性が重要です。
高強度トレーニングは中枢神経系に負荷をかけ、運動単位の発火頻度を一時的に低下させることがあります(Häkkinen, 1993)。
例えば月曜日の高重量スクワットは中枢神経系に強いストレスを与え、火曜日のベンチプレスでの最大筋力や動作の「キレ」が5〜10%程度低下する可能性があります。
ただし下半身と胸は異なる筋群を対象とする為に局所的な末梢神経系の疲労の影響は限定的です。
もし月曜日のトレーニングが中〜低強度(1RMの60%以下)であれば、発火頻度への影響はほぼ無視できるレベルに抑えられます。
活動電位と神経伝達物質への影響
活動電位は神経や筋細胞の膜電位が変化して信号を伝える現象で、筋収縮の引き金となります。
このプロセスには神経筋接合部で放出されるアセチルコリンや、興奮状態を高めるカテコールアミン(ドーパミン、ノルアドレナリンなど)が関与します。
連日の高強度トレーニングはアセチルコリンの合成や再補充を妨げ、活動電位の伝達効率を低下させることがあります(Fitts, 2008)。
またカテコールアミンの過剰な消費は、副腎疲労や集中力低下を引き起こす可能性があり、これにより火曜日の胸トレーニングで、反応速度や筋力発揮の効率がわずかに低下することが考えられます。
特にベンチプレスなどの高重量コンパウンド種目では、フォームの安定性や爆発力が影響を受ける可能性があります。
ただし適切な回復(睡眠7〜9時間、十分なタンパク質や炭水化物の摂取)があれば、活動電位の機能は比較的早く回復します。
電解質(ナトリウム、カリウム)やビタミンB群、マグネシウムの補給も神経伝達物質の合成をサポートし、疲労を軽減します。
実践的な対策:神経系の疲労を最小限に抑えるには?連日の高強度トレーニングによる神経系の疲労を軽減するためには、以下の対策が有効です
- トレーニングの分割と強度管理
- 高強度コンパウンド種目を連日行う場合、間に低強度の日や休息日を挟むことが理想です。
- 例えば、月曜に高強度の下半身トレーニングを行ったら、火曜は中〜低強度の胸トレーニング(8〜12レップ)やテクニック重視のセッションにすると、神経系の負担を軽減できます。
- 研究では、トレーニングのボリュームと強度を適切に管理することで、神経系の疲労を抑えつつ適応を促せることが示されています(Schoenfeld, 2010)。
- 回復を促す習慣:
- 睡眠:質の高い睡眠(7〜9時間)は、神経系の回復に不可欠です。
- 栄養:タンパク質、炭水化物、ビタミンB群、マグネシウムを十分摂取し、神経伝達物質の合成をサポートしましょう。
- アクティブリカバリー:軽いストレッチやウォーキングで血流を改善し、回復を早めます。
- パフォーマンスのモニタリング:
- トレーニング中に集中力の低下や筋力の明らかな減少を感じたら、それは神経系の疲労が蓄積しているサインかもしれません、この場合では強度を落としたり、休息日を増やすことを検討しましょう。
まとめ:バランスが鍵を握る
仮に月曜日の高強度下半身トレーニングを行った場合、火曜日の胸トレーニングに軽度〜中程度の影響を与える可能性があります。
具体的には活動単位の発火頻度の低下や、活動電位の伝達効率のわずかな低下がベンチプレスなどの高負荷種目でのパフォーマンスに影響するかもしれません。
ただし下半身と胸は異なる筋群を対象とする為に筋繊維自体の疲労の影響は少なく、主に中枢神経系の疲労が問題となります。
適切なトレーニング計画(強度とボリュームの管理)、十分な睡眠と栄養、アクティブリカバリーを取り入れる事で神経系の疲労を最小限に抑え、効率的なトレーニングを継続できます。
自分の体調やパフォーマンスをモニタリングしながら、無理のないスケジュールを組む事が長期的な筋力向上の鍵となります。
トレーニングはがむしゃらに行うだけでは無く計画性、特に疲労管理が重要だと言う話です。
滋賀県大津市月輪1丁目3-8 アル・プラザ瀬田4F 女性専用フィットネスLBC
無料体験随時受付中