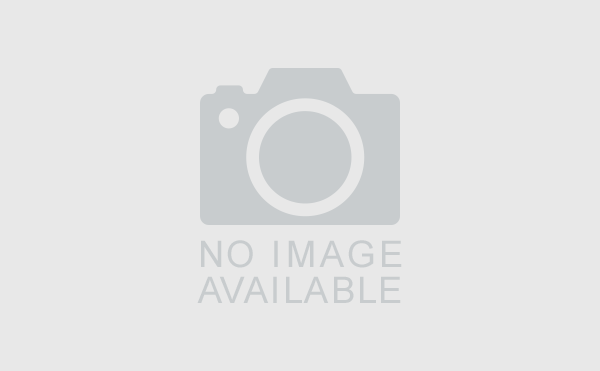フィットネス―疲労理論と超回復理論

滋賀県大津市瀬田のトレーニングジム 女性専用フィットネスLBCです。
トレーニングで目標を達成するには、そのトレーニングに対して身体がどのような反応するかを理解することが重要です。
その鍵となるのが「パフォーマンス = フィットネス - 疲労」という式を基にしたフィットネス―疲労理論です。
この理論はトレーニング効果を最大化する為の一つの道筋を示します。
一方で似た概念として超回復理論もありますが、両者はアプローチや焦点が異なります。
今フィットネス―疲労理論を中心に超回復理論との違いをエビデンスに基づいて、初心者にもわかりやすく解説した文は以下の通りです。
フィットネス―疲労理論とは?
フィットネス―疲労理論は1980年代にバニスター博士らによって提唱されたモデルで、トレーニングによるパフォーマンスの変化を説明します(Bannister et al., 1986)。
その核心は「パフォーマンス = フィットネス - 疲労」というシンプルな式です。
- フィットネス:トレーニングで向上する身体の適応能力で、筋力(Schoenfeld, 2010)、持久力(Holloszy & Coyle, 1984)、技術などがこれに含まれます。
- 疲労:トレーニングによる一時的なストレスで、筋肉の微細な損傷(Cheung et al., 2003)、エネルギーの枯渇、神経系の疲労などが該当します。
- パフォーマンス:フィットネスから疲労を引いた結果で、トレーニング直後は疲労が大きくパフォーマンスが下がりますが休息で疲労が減ると、フィットネスの効果が現れます。
トレーニングを「家を強くするリフォーム」として例えると、フィットネスは家の強化、疲労は工事中の散らかりで、片付け(回復)が終われば、家は以前より快適(パフォーマンス向上)になり、このバランスが重要となります。
超回復理論とは?
超回復理論はトレーニング後の回復プロセスに焦点を当てたモデルです。
トレーニングで身体にストレス(例:筋繊維の損傷)が加わる事で一時的にパフォーマンスが低下しますが、適切な休息と栄養により身体は元のレベルを超えた状態に回復します(Zatsiorsky & Kraemer, 2006)。
一般的にはウェイトトレーニング後に48~72時間休息すると筋肉が修復・強化され、次のセッションでより重い重量を扱えるようになります(Phillips et al., 1997)。
フィットネス―疲労理論と超回復理論の違い
この2つの理論はトレーニング効果を説明する点で似ていますが、以下の点で異なります。
1. 目的と焦点
- フィットネス―疲労理論はパフォーマンスを長期的に最適化することを目的とします。 フィットネスと疲労のバランスを管理し、大会や試合でのピークパフォーマンスを引き出します。トレーニングサイクル全体(数週間~数か月)を扱います(Issurin, 2010)。
- 超回復理論は単一のトレーニングセッション後の回復と適応に焦点を当て、筋肉やエネルギーシステムが回復し、元のレベルを超えるタイミングを重視します(Schoenfeld, 2010)。
- 例:ベンチプレス後に48時間休息し、胸の筋肉が強化されて次のセッションで重量アップ。
違い:フィットネス―疲労理論は長期的なパフォーマンス管理、超回復理論は短期的な回復プロセスに特化。
2. 時間的範囲
- フィットネス―疲労理論は数週間~数か月の長期的な視点でのトレーニング結果に着目。フィットネスは徐々に蓄積し、疲労はトレーニングごとに変動。ピリオダイゼーション(計画的な負荷調整、期分け)でバランスを取ります。
- 超回復理論は数時間~数日の短期的視点、単一セッション後の筋肉修復やグリコーゲン補充を扱います(Cheung et al., 2003)。
違い:フィットネス―疲労理論はトレーニング計画全体、超回復理論は個々のセッションの回復を対象。
3. 適用範囲
- フィットネス―疲労理論はランニング、ウエイトリフティング、サッカーなどの幅広いスポーツに適用。アスリートやフィットネス愛好者がピークパフォーマンスを目指す際に有効。
- 超回復理論は主に筋力トレーニングや筋肥大に適用。ボディビルダーや筋力向上を目指す人に特化。
違い:フィットネス―疲労理論は多様なスポーツ、超回復理論は主に筋力トレーニング中心。
「パフォーマンス = フィットネス - 疲労」の実例マラソン選手を例に、フィットネス―疲労理論を考えてみましょう。
週5日のランニングで持久力(フィットネス)が向上しますが、筋肉痛やエネルギー枯渇で疲労も溜まります。
この時点でレースを走ると疲労がパフォーマンスを下げてしまいますが、レース2週間前にトレーニング量を減らす(テーパリング)事で疲労が減少し、フィットネスの効果が現れます。
研究では、テーパリングでパフォーマンスが5~10%向上するとされています(Mujika & Padilla, 2003)。
一方で超回復理論では、例えばスクワット後に48~72時間休息すると、脚の筋肉が修復・強化され、次のセッションでより高い負荷に挑戦可能。これが超回復の典型例です(Phillips et al., 1997)。
実践:理論をトレーニングに活かす
フィットネス―疲労理論を活用するには以下のポイントを意識しましょう。
1. トレーニング負荷の管理強度、量、頻度を計画的に調整します。
例えば週3回の筋力トレーニング(高強度2回、低強度1回)に休息日を挟む事で疲労が溜まり過ぎを防ぎます。
過剰なトレーニングはオーバートレーニング症候群のリスクを高めてしまいます(Meeusen et al., 2013)。
2. 回復を最適化疲労を減らし、フィットネスの効果を引き出すには、回復が重要です。
- 睡眠:7~9時間の質の高い睡眠で筋肉やホルモンが回復(Samuels, 2008)。
- 栄養:タンパク質(1.6~2.2g/kg/日)で筋修復を促進、炭水化物でグリコーゲンを補充(Morton et al., 2018)。
- アクティブリカバリー:軽いストレッチやウォーキングで血流を促し、回復を早めます(Dupuy et al., 2018)。
3. ピリオダイゼーションの活用
トレーニングを高負荷期と低負荷期に分けます。
4週間の高負荷トレーニング後に1週間のディロード(軽負荷)を入れる事で疲労が解消され、パフォーマンスが向上します(Issurin, 2010)。
超回復理論を活かすなら筋群ごとに48~72時間の休息を確保し、例えば月曜に胸のトレーニング、木曜に再び胸といったスケジュールが効果的です。
注意点:個人差を考慮
どちらの理論も個人差が大きく影響します。
遺伝やトレーニング経験、年齢で回復時間やフィットネスの向上速度は異なります(Bouchard et al., 1999)。
初心者は筋肉痛が長引きやすく、ベテランは回復が早い傾向があります。
RPE(感覚的努力尺度)や心拍変動(HRV)で疲労をチェックする事で自分のペースがわかります(Halson, 2014)。
まとめ:自分に合った理論でパフォーマンスアップ
「パフォーマンス = フィットネス - 疲労」はトレーニングの効果を最大化するための強力な指針です。
フィットネス―疲労理論は長期的な計画でピークパフォーマンスを目指す人に、超回復理論は筋力トレーニング後の回復タイミングを重視する人に最適です。
例えばマラソンならテーパリングで疲労を管理、筋トレなら48~72時間の休息で超回復を狙いましょう。
自分の目標に合わせてこの2つの理論を活用すれば効率的に成果を上げられます。
何事も計画性が重要だと言う話です。
滋賀県大津市月輪1丁目3-8 アル・プラザ瀬田4F 女性専用フィットネスLBC
無料体験随時受付中